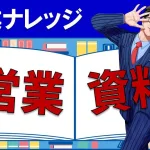直行直帰の営業スタイルは様々な業種業態で採用されています。
中には「サボれる」「楽(ラク)」という都市伝説的な話もあったりするので、今回は直行直帰制度について解説したいと思います。
目次
直行直帰するメリット&デメリット
営業職として働いていると、現場によって直行直帰できる場合がありますよね。
ちなみに、直行直帰は「ちょっこうちょっき」と読みます。
一般的な会社員であれば、オフィスに出社して打刻するのが当たり前ですが、営業職だけは業務効率化の観点から、遠方のお客様へ訪問するときに自宅から直接向かう「直行」が許されているのです。
そのようなケースでは、行きと同様に帰りもオフィスへ立ち寄ることなく、そのまま自宅に帰れる「直帰」になるケースが多いようです。
営業をサボることもできちゃう!?
直行直帰を採用するメリットは以下の通りです。
- 営業職の負担を軽減する
- 時間の無駄をなくす
- 業務効率を上げる
帰り際にオフィスへ立ち寄るのは時間をロスするだけでなく、精神的&身体的な負担も大きくなってしまいます。
そのような点を改善した結果、出来上がった商習慣が直行直帰なのです。
つまり営業パーソンにとって直行直帰は便利な仕組みで、「できればずっと直行直帰したい!」と言う人もいるほどなのです。
しかし実際に営業職として直行直帰してみると、運用方法など様々なデメリットもあることに気付きます。
例えば直行直帰であれば、その日は単独行動になるので、考え方によってはいくらでもサボることができるのです。
ということは、日常的に直行直帰が許されている会社の場合、毎日かなりの勤務時間を自由に使うことができてしまいます。
これは雇用主(=企業)にとってかなり大きなリスクだと思います。
仕事中なのに旅行気分で休憩したり、一日オフみたいに満喫されたらたまったもんじゃありません。
オフィスに立ち寄る必要がないので、上司や同僚に監視されることがなく、社用車で音楽を聴きながらドライブ気分を満喫している外回り営業マンもいるのです。
直行直帰のルールはどうする?
もし直行直帰の仕組みを導入したいのであれば、それなりのルールを整えなければいけません。
直行直帰型の営業スタイルが一般化されたとはいえ、実際に労使間でそれを管理するシステムを導入しているという事例はそれほど多くありません。
直行直帰では「自宅→商談→帰宅」という流れになるので、物理的にタイムカードを切ることができません。
とはいっても、直行直帰する場合には「本当に仕事をしているのか?」ということをきちんと管理しなければいけないので、そのための仕組みを考えなければいけません。
「直行直帰で営業していると思ったら、実はマンガ喫茶でサボっていた!」なんてことも十分あり得るのです。
- アポの時刻に遅刻をしていた
- 実質的に早退していた
- 営業車で昼寝していた
このようなことも起こり得るので注意が必要です。
直行直帰を管理する方法
このような問題点がある一方、ITツールを活用して管理体制を整えていこうという動きもみられます。
典型的なのは勤怠管理についてです。
従来式のアナログなタイムカードではなく、オンラインで打刻ができるITシステムを取り入れて管理する方法があります。
それであれば、営業マンが持っているスマートフォンでも打刻できるので、形式的には稼働時間を管理できるでしょう。
仕事を始める時にオンライン打刻し、仕事を終えたらまた打刻するというルールで運用すれば、外出先でも問題ありません。
さらに厳密な管理をしている企業では、スマートフォンを貸与してGPS管理しているケースもあります。
この仕組みでは打刻したタイミングに限らず、日中行動したルートまで把握できるので、もしサボっている場合にはすぐにバレてしまいます。
他の職種と平等感を持たせるという目的でも、このような勤怠管理システムの導入が進められているのです。
その他にも、商談が終わる度に上司に連絡するように指示しているケースもあります。
外回りをする営業マンとしてはめんどくさい話ですが、きちんと管理する為には、誰かが面倒な部分を巻き取らなければいけないのです。
残業時間はどうすればいい?
直行直帰の場合には勤怠管理が難しく、実際にいつからいつまで働いたのかを明確にするのが難しいのも確かです。
コンプライアンス順守の観点では残業時間を徹底管理して、適切な残業代を支払うことが求められるので、この辺りをクリアにしておかないと後々問題にもなりかねません。
給与&賃金計算する上では、時間外労働・休日労働に関する協定(36(サブロク)協定)も意識しなければいけません。
外回りの営業職ではサービス残業が常態化しているので、直行直帰の場合にはその状況がますます顕著になるはずです。
働いたからには、その分の残業手当を支給するのが当たり前なので、経営者は事前に仕組みを作っておかなければいけません。
それを意識していないと、ある日突然、従業員から訴えられることもあるのです。
みなし残業の活用が多い
それでは、直行直帰OKにしている企業では、どのような仕組みで残業代を管理しているのでしょうか?
オンラインの勤怠管理システムを導入している企業を除くと、「みなし残業を定める」か「完全なサービス残業」になっているかの2択が一般的だと思います。
みなし残業は、企業があらかじめ残業代分を支給する仕組みなので、所定の手続きを済ませれば法的な問題はありません。
残業代として支給された分の残業をしても、全く残業をしなくても支給額が一定なので、同じ残業手当が支払われることになります。
これはある意味で、現場に即した機動的な残業代支給方法と言えるでしょう。
しかし、もう一方の「サービス残業」は基本的にNGなので、すぐに改めた方が良いと思います。
サービス残業とは、残業代が出ないのに従業員が残業する仕組みのことです。
責任感がある人は、自分の仕事が終わっていないと、たとえ残業代が出なくても働いてしまいますが、これは経営者がOKを出したからとか、従業員が同意したからOKということにはなりません。
そもそもサービス残業させること自体が違法行為なのです。
なので、もし社員がサービス残業をしているのであれば、すぐにその仕組みは改めるべきでしょう。
しかし一方で、営業職には「ノルマ」という必達すべき予算が課せられており、ノルマ達成できるまで働くのが当たり前という暗黙の了解があります。
そのような考え方が強い会社では、勤務時間が脇に置かれ、ノルマを達成したか否かだけが問われてきます。
このように、残業時間に対する捉え方は企業文化によって大きく異なるので、直行直帰の転職先を選ぶときには注意しましょう。
直行直帰は楽(ラク)
直行直帰できる営業職は、一般的に楽(ラク)だと言われています。
営業職のイメージは、いつも大量のノルマを課されて、ライバルと競争するように働かなければならない…
そのような激しい営業会社があるのも確かですが、直行直帰で働くことができれば上司や同僚に会うことはありません。
しかも直行する場合は会社に行く場合と比べて、時間的な余裕ができるのは確かだと思います。
毎朝9時に会社に行く場合は、通勤時間を含めて行動しなければいけませんが、直行する場合には自宅を9時に出れば良いのです。
そう考えた場合、30分から1時間ぐらいは遅く起きれるはずです。
これは直帰するときにも同じだと思います。
18時に仕事が終わる場合、そこから自宅に着くまでは30分から1時間ほどかかるので、19時頃帰宅という感じになると思いますが、直帰の場合には18時に帰宅してそこでオンライン打刻すれば良いので、会社から帰宅するよりも1時間ほど早く家に到着できると思います。
そして、外回り営業している最中は「連絡しなくてOK」という会社もあるので、そのような場合には最大パフォーマンスが追求できるでしょう。
出勤や退勤に関する厳しさもなく、定時通りに働くように促されることもないことから、自由なスケジュールで働けるのも魅力です。
出張する時には、アポイントの合間に観光することもできるはずです。
このように自由である反面、サボり癖があったり、怠けてしまう人は注意が必要な働き方だと思います。
直行直帰で働いている営業マンには、全ての業務を自己管理する能力や、強い精神力が求められるはずです。
一人だと怠けてしまう人や、上司から監視されていた方がパフォーマンスが良い人には向かない働き方なのです。
直行直帰で働く心構え
ここまで解説してきたように、「気楽な働き方が好み」というなら、直行直帰型で働くのがおすすめです。
営業職は特殊な仕事なので、きちんと実績さえ出せば誰からも文句を言われることがない職業です。
そのような職種であるからこそ、サボっていても、楽な働き方をしても大丈夫なのです。
なので、もし直行直帰で働きたい場合には「きちんと結果を出す」という心構えが必要だと思います。
上司や同僚に会う機会が少なくなっても、お客様とは毎日会ったり、できるだけたくさん話すことが大切だと思います。
顧客と良い関係が築ければ、営業成績もどんどん良くなっていくからです。
前向きに仕事を楽しんでいれば、サボったり怠けたりすることも無いでしょう。
「どうやってサボるか?」を考えるのではなく、心から「仕事が楽しい!」と思えることが重要なのです。
もし今の仕事に満足していないなら、転職することも検討しましょう。