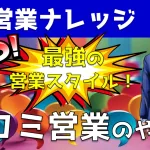戦国武将の生き様は、日本史ファンを惹きつけてやみません。
そのような名将と呼ばれる武士の残したカッコイイ言葉は、今でも多くの人々に語り継がれています。
そこで今回は、ビジネスに使える戦国武将の名言をまとめてみました。
組織のマネージャーや、リーダーシップを発揮したい人は是非ご覧ください。
目次
楠木正成の名言
足ることを知って、及ばぬことを思うな。
楠木正成は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した戦国武将です。
この言葉の意味は「足りていることに目を向けて、足りないことを気にするのはやめなさい」ということです。
人にはそれぞれ長所・短所がありますが、完璧な人間など存在しないのです。
合戦の勝負、必ずしも大勢小勢に依らず、ただ士卒の志を一つにするとせざるとなり。
チームスポーツには「チーム一丸となって戦う」という言葉がありますよね。
まさにこの「ワンチーム」になることを推奨している名言なのです。
この名言には「戦いの勝敗は、必ずしも兵の数が多いか少ないかで決まるのではなく、兵士の心をひとつにできるかどうかで決まるのだ」という意味合いがあります。
たとえ少ない兵力だったとしても、まとまりのある組織は強いのです。
足利尊氏の名言
他人の悪をよく見る者は、己が悪これを見ず。
大企業に入ると、みんな足の引っ張り合いをしますよね。
大会社では減点方式が採用されているので、自分が出世するために人の悪いところや、他人の粗探しをしてしまうのです。
この名言には「他人の欠点や悪い部分ばかりを見て批判する人は、自分の欠点や悪い部分を見ることがない」という意味が込められています。
いくら人の粗探しをしたところで、自分自身は全く成長できないのです。
文武両道は車輪のごとし。
一輪欠ければ人を渡さず。
強い男になる為には、武道を学ぶだけでなく、優れた知識も必要なのです。
現代ビジネスに置き換えてみると「知識と行動力」だと言えるでしょう。
知識だけあっても頭でっかちで行動力がありません。
行動力があったとしても、見切り発車であれば失敗の連続です。
この二つがバランス良く揃わなければ、成功を掴み取ることなどできないのです。
天下を司る人は、天下を救い養う役なり。
然る則は吾身の苦は、天地に溢るる程こそあるべけれ。
サラリーマンであれば、誰でも出世したいと思いますよね。
しかし人の上に立つということは、それなりの責任も求められるので、決して楽なポジションではありません。
室町幕府を開いた足利尊氏は、「政治を行うものは、人々を救うのが役目である。だからこそ自分の苦労は天地に溢れるほどたくさんあるはず」と考えていたのです。
山名宗全の名言
およそ例という文字をば、尚後は時という文字にかへて御心あるべし。
山名宗全は、戦国時代の守護大名です。
「過去の例にとらわれず、その時々に応じて対処することが重要である」と述べたこの言葉は、リーダーが肝に銘じておくべき名言だと思います。
ちゃんとした理由があれば、朝令暮改を恐れず、潔く方向転換することも必要でしょう。
そのような勇気のある意思決定がリーダーに求められるのです。
朝倉孝景の名言
人の上に立つ主人たるべき者は、不動明王と愛染明王のごとくあれかし。
室町時代の守護大名であった朝倉孝景の名言です。
人の上に立つリーダーは、厳しいだけでは務まりませんが、優しいだけでも駄目なのです。
その両方を兼ね備えた人だけが、本当のリーダーになれるのです。
細川勝元の名言
短慮功を成さず。
この言葉は、応仁の乱で東軍の総大将を務めた細川勝元の名言です。
その意味は「短気の人は何事も成し遂げられない」ということですが、つまりリーダーとなる人はアンガーマネジメントを身につけるべきなのです。
その時の感情に任せて動くと、手痛いしっぺ返しを食らうことになるでしょう。
毛利元就の名言
一年の計は春にあり、一月の計は朔にあり、一日の計は鶏鳴にあり。
この言葉は「三本の矢」でおなじみの毛利元就が残した名言です。
「一年の計画は年のはじめに、一ヶ月の計画はその月の最初の日に、そして一日の計画は鶏が鳴く早朝に立てるべきだ」と述べたのです。
計画を立てたら、早めに実行しましょう!
立花道雪の名言
本来弱い士卒というものはいない。
もし弱い者がいれば、その人が悪いのではなく大将が励まさないことに罪がある。
この言葉は「仕事のできない部下がいる場合、その上司にも責任がある」と言っているのです。
優秀な部下に育てるのは上司の役目です。
リーダーを目指す人は肝に銘じておきましょう。
今川義元の名言
昨日なし明日またしらぬ人はただ今日のうちこそ命なりけれ。
この言葉は「昨日はもう過ぎ去ってしまった。明日はまたどうなるか分からない。人は今日一日を生きることがすべてである」という意味の名言です。
桶狭間の戦いで織田信長と対決した今川義元は「今を生きろ」と進言したのです。
命のやり取りをしていた戦国武将らしい言葉ですよね。
武田信玄の名言
為せば成る、為さねば成らぬ成る業を、成らぬと捨つる人のはかなさ。
この言葉の意味は「物事は努力すれば必ず成し遂げられる。努力すればできることを最初からできないと諦めてしまうのは人間の弱さである」ということです。
人気漫画から生まれた「諦めたらそこで試合終了ですよ」という有名な名言もありますよね。
それと同じで、最初から諦めてしまっては何も始まらないのです。
百人のうち九十九人に誉めらるるは、善き者にあらず。
これはビジネスの現場でもよく聞く言葉ですよね。
多くの人から認められているから優秀だということにはなりません。
褒める人の中には、嘘をついていたり、ポジショントークをしている人もいるからです。
もし起業する場合には「10人中9人が反対するのであれば成功する」と言われます。
もし逆に「10人中9人が賛成する」のであれば、そのビジネスは失敗する可能性が高いのです。
この考え方は、特に経営者が持っておくべき思考術だと思います。
人は城。
人は石垣。
人は堀。
情けは味方。
仇は敵なり。
戦国最強と言われていた武田信玄は、兵の重要性を理解していました。
人材を適材適所に配置し、モチベーションをアップさせれば、期待以上の成果を発揮してくれるのです。
この名言には、組織をコントロールする術が詰まっているように感じます。
高坂昌信の名言
人を讃るに能き証拠を引き、誹るに悪き証拠を引くが本道。
この言葉には「人を褒める時はその人が優れていることを示す証拠を出し、反対に人を批判する時にはその人が悪いことを示す証拠をが重要である」という意味があります。
感情論で語るのではなく、ちゃんと論理的に説明しないと、部下は納得しないのです。
公平正当な評価を心掛けましょう。
上杉謙信の名言
運は天にあり、鎧は胸にあり、手柄は足にあり。
この言葉の意味は「合戦の勝敗は天が決めることなので、自分にはどうにもできない。自分にできるのは鎧をまとって心身を強固にし、足を動かして手柄を上げることだけだ」ということです。
つまり色々考えて悶々とするよりも、とにかく行動するのを推奨したのです。
心に勇みある時は悔やむことなし。
自分が正しいと信じたことであれば、失敗しても後悔は少ないですよね。
勇気ある行動こそが、悔いのない人生をつくるのです。
我は兵を以て戦ひを決せん。
塩を以て敵を屈せしむる事をせじ。
上杉謙信は、宿敵である武田信玄が塩の輸送を止められているのを知ると、敵対する立場でありながら武田信玄に塩を送ったそうです。
この逸話から生まれた「敵に塩を送る」ということわざは、今でも語り継がれています。
宇喜多直家の名言
一人で事にあたるな。
この名言は「戦国の三梟雄」と言われた宇喜多直家の名言です。
何でも自分一人で出来ると思うのは危険な発想だと思います。
仕事というのは自分一人で出来るはずがなく、周りの支援があってからこそ実現するのです。
小早川隆景の名言
すぐわかりましたという人間に、わかったためしはない。
部下に仕事を任せる場合、その内容を指示すると思いますが、すぐに「わかりました」という人には注意しましょう。
きちんと理解していない可能性があるので、指示した内容をもう一度本人の口から説明してもらうのが理想的でしょう。
これは仕事でのミスをなくし、リスクヘッジすることに繋がっていきます。
織田信長の名言
絶対は絶対にない。
「絶対に大丈夫」と考えると、隙ができてしまいます。
これはビジネスにおいて非常に危うい状態だと思います。
もし予想通りにいかなかった場合、対処が遅れて、取り返しのつかない事態にもなり得るからです。
絶対に過信することはやめましょう。
組織に貢献してくれるのは「優秀な者」よりも「能力は並の上だが、忠実な者」のほうだ。
マネージャーは、できる限り「優秀な人を集めたい!」と考えますよね。
しかしそれよりも重要なポイントは「忠実である」ことなのです。
優秀な人には成功体験がたくさんあるので、自分の考えをなかなか曲げられません。
そのような人をコントロールするのは大変なので「忠実な人」を集めるようにしましょう。
いつの時代も変わり物が世の中を変える。
異端者を受け入れる器量が武将には必要である。
織田信長の先見性が垣間見える言葉ですよね。
現在ビジネスでは「多様性(diversity)」が叫ばれていますが、まさにそれを体現するような名言だと思います。
豊臣秀吉の名言
負けると思えば負ける。
勝つと思えば勝つ。
逆になろうと、人には勝つと言い聞かすべし。
やる前から気持ちで負けてしまうと、何事も成し遂げられません。
特にチームリーダーであれば、メンバーのモチベーションアップは欠かせませんよね。
常に高いモチベーションを維持してもらうには、豊臣秀吉の考え方が有効的かもしれません。
障子を開けてみよ、外は広いぞ。
会社内のメンバーや、同じ友人・知人とばかり話していると、視野が狭くなってしまいます。
積極的に社外の人と交流していきましょう。
藤堂高虎の名言
己の立場を明確にできないものこそ、いざという時に一番頼りにならない。
この名言は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した藤堂高虎の言葉です。
ビジネスパーソンは、自分の意見を持たなければいけません。
曖昧な態度では人から信頼を得ることができないのです。
徳川家康の名言
及ばざるは過ぎたるより勝れり。
この言葉は「足りないことは、ありすぎるよりも優れている」という意味です。
自分が未熟だと思えば、成長するように努力しますよね。
しかし、自分は優秀だと慢心してしまえば、そこで成長は止まってしまうのです。
勝つことばかりを知って、負くることを知らざれば、害その身に至る。
失敗することを恐れるかもしれませんが、失敗することは大きな糧となるのです。
恐れずに挑戦していきましょう。
山内一豊の名言
命を捨てる覚悟で運を拾わねば、運などは拾えるものではない。
簡単に名声を手に入れることはできないのです。
命を懸けて取り組むからこそ偉業が成し遂げられるのです。
加藤清正の名言
人は一代、名は末代。
天晴武士の心かな。
加藤清正は熊本藩の初代藩主です。
人生は一回きりですが、その人生で成し遂げた偉業は、後世まで語り継がれます。
そのような心構えで、死を恐れない人こそが「武士」であると語ったのです。
伊達政宗の名言
時を移さずに行うのが勇将の本望である。
早く出立せよ。
慎重に考えすぎると、行動できなくなります。
思い切った行動には勇気が必要ですが、その決断力こそがリーダーに求められているのです。
仁に過ぎれば弱くなる。
義に過ぎれば固くなる。
礼に過ぎればへつらいとなる。
智に過ぎれば嘘をつく。
信に過ぎれば損をする。
「独眼竜」と呼ばれた武将 伊達政宗の名言です。
この考えは中国儒教の教えにある「仁・義・礼・智・信」が元になった名言です。
「人を大切にしすぎると相手のためにならない。正義にこだわりすぎると考えが固くなる。礼儀正しくしすぎると相手に不快感を与える。知恵がありすぎると嘘をつく。人を信用しすぎると損をする。」
ビジネスだけでなく、人生においての格言になるでしょう。
井伊直孝の名言
義に背けば勝っても勝ちではなく、義を貫けば負けても負けではない。
この名言にある「義」とは、人付き合いで守るべき道理のことです。
相手のことを尊重し、仁義を尽くしてこそ、本当の勝利がもたらされるのです。
まとめ
ここまで戦国武将の名言集をご紹介してきました。
どれも勇ましさのある格言ばかりですよね。
ぜひこの中からあなた好みの「座右の銘」を見つけてください。