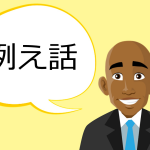営業部長は経営戦略上の重要ポジションだといえます。
ある意味では「社長の次に重要なポジション」といっても過言ではないでしょう。
そこで今回は、営業部長が持つべき心得や考え方、必要なスキルなどを詳しく解説していきたいと思います。
目次
営業部長の役割とは?
営業部長は、その名の通り「営業部の長」であり営業部のトップとして、営業部全体を統括する立場にあります。
つまり、営業部でも一課・二課・三課などと分かれていた場合、課長は自分の課だけを管理すれば良いですが、部長になるとそれら全てを統率しなければいけません。
実質的には課長や係長などに実務を任せることになりますが、営業部長もチームメンバーをしっかりサポートして、引っ張っていく存在なのです。
大きな会社では「営業本部長」「営業統括」という肩書きや役職がありますが、この場合は執行役員などの取締役クラスが兼務することも少なくありません。
営業部長は責任重大
営業部長最大の役割は会社予算の達成と、売上の最大化を目指すことです。
「会社の予算達成」とは、今年度の事業予算を目標通り達成することを意味しています。
そして「売上の最大化」とは、将来への投資を意味します。
今年度は無事に目標達成できるとしても、来年度、再来年度はどうなるか分かりません。
会社の売上を最大化させることが出来なければ、営業部長としての存在意義が問われることになります。
なので早い段階から営業戦略上の種まきを開始して、来年再来年に備えるのです。
営業部は会社の売上を左右する重要な仕事になるので、責任が重い仕事だと言われます。
営業部長は現場管理者として、事業予算や目標を立てて、その高い目標を達成しなければいけないので、プレッシャーが大きくストレスも多いはずです。
気になる営業部長の給料についてですが、これは会社の給与システムによっても変わりますが支店長クラスと同程度になることが多いでしょう。
大企業の部長ともなると、年収1,000万円を超えることは当たり前だと思います。
プレイングマネージャーとして働く
大企業ではあまり無いケースかもしれませんが、中小ベンチャー企業の営業部長はプレイングマネージャーとして現場で活躍している人が多いです。
営業部長とはいえ、まだまだ現役のトップセールスとして働いている人もいるのです。
しかし、名刺には「営業部長」「営業責任者」という肩書きを使えるので、これは営業戦略上大きなアドバンテージになるはずです。
このメリットを営業活動に100%活かしていきましょう。
営業部長は「決裁者」になります。
営業部長であれば値引き対応も含めて決裁権があるはずなので、その場で商談をまとめる即決営業が実現できるはずです。
もしこれができないようであれば、本当の意味で事業責任者ではありません。
部下と営業同行して即決営業を実践することで、人材育成にも繋がっていくはずです。
営業統括に求められるスキル
課長から部長に昇進するということは、会社内で評価されたことを意味します。
その場合は、給料など年収に関わることだけではなく、チームでの役割や仕事内容にも大きな違いが出てきます。
課長から部長になる前に心得るべき事項は2つあるので、ここで解説していきたいと思います。
- リーダーシップ
- マネジメント
リーダーシップを身に付ける
1つ目は「リーダーシップ」です。
あなたは「リーダーシップ」をきちんと説明することができるでしょうか?
リーダーシップとは、組織やチームを導く力のことをいいます。
事業責任者になったからには、その会社の代表者であるという自覚が必要です。
これだけでは抽象的なので、もう少し具体的にリーダーシップを解説すると、「ビジョンを共有すること」だと言えます。
例えばあなたの会社が販売している製品(プロダクト)があって、「その製品を年間1,000件受注していくと、3年後にはどんな会社になるか?」というのがビジョンなのです。
リーダーシップがある人とは、この将来像をまるで3年後の会社に行って見てきたかのように具体的、かつ明確に語ることができる人です。
これはつまり道標とも言い換えることができ、事業の「灯台」になるべきものです。
会社経営とは目的地がわからない大海原にいるようなものなので、将来どこに辿り着くのか従業員は全くわかっていません。
それを理解しているのは経営者や事業責任者だけです。
そんな時に、「あと3年間頑張れば、絶対あの街の灯台に辿り着くからみんな頑張ろう!」と言われれば具体的なゴールがイメージできます。
そして自分がコミットメントした通りに、事業を着地させるのです。
このようなビジョンの共有ができると、チームメンバーは具体的な将来像がイメージができるので、仕事に対してのモチベーションもアップしていきます。
逆にビジョンの共有ができないと、真っ暗のトンネルを駆け抜けている状態なので、チームメンバーは出口が見えず不安になってしまいます。
なので、営業部長はチームメンバーにビジョンの共有ができる”リーダーシップスキル”を身につけるべきなのです。
リーダーシップが上手く使えるようになっていくと、営業チームを今よりも高みに導くことができるようになっていきます。
これは組織全体の底上げにつながっていくので、営業責任者にとって重要な役割だと思います。
そのような観点で見ると、課長もリーダシップがあった方が良いと思われがちですが、現実的にはあまり求めない方がいいと思います。
「船頭多くして山を登る」ということわざがあります。
意思決定するトップが組織に何人もいると、現場が混乱して、最悪のケースではチームが崩壊するという有名なことわざです。
このことわざが示す通り、リーダーシップを発揮するリーダーは、チーム内にたった一人で良いのです。
リーダーシップについて詳しく知りたい場合には、下の記事をご覧ください。
マネジメント能力が必須
課長から部長になる前に心得るべき事項2つ目は「マネジメント」です。
マネジメントに関しては有名な書籍がたくさん出ているので、まずはそのような本を読んで勉強するのもおすすめです。

部長は「マネージャー」「事業責任者」とも呼ばれる立場なので、会社の経営方針や戦略を部下に教育するという仕事があります。
目標を立てて成果を出すために、人の配置や配分といった業務プロセスの設計などの業務マネジメントが代表的なものでしょう。
また、人材マネジメントやモチベーションアップも部長の大切な仕事です。
- 次期部長や課長の器に相応しい人物を育てること
- 働きやすい環境を作ること
- 万が一に備えてリスクマネジメント
などが全てマネジメントに関連する仕事になります。
つまり、マネジメントとは「組織を管理して維持させる」ことなのです。
リーダーシップとは今よりも高みを目指すことなので、上向きのチャレンジ思考です。
それに加えて、「最低でも現状維持する」というマネジメント思考が足されることで、土台がしっかりした組織が出来上がります。
プレイヤーが力を発揮できるよう土台を固めて、さらなる高みへ引っ張っていくというのが営業部長という存在なのです。
営業部長になれる人の資質
課長止まりではなく、部長職に昇進する人にはどのような特徴があるのでしょうか。
まず挙げられるのが、頼られる存在であるということです。
この頼られるというのは、部下からだけではなく上司や社長からも頼られるということで
側面があります。
部下から頼られるということは、それだけ寛容ということを意味し、上司から頼られるということは信頼感があって実行力もあるということになります。
部長職というのは管理職になるので、頼りがいのある人物ということが必要不可欠な要素なのです。
仕事を部下に任せられること
営業部長という責任ある立場になった場合、なかなか難しいのが「部下に仕事を任せること」です。
これは簡単なように思えて、とても難しいことだと思います。
営業部長として活躍している人は、総じて優秀な人が多いからです。
例えば、ある見込み案件があったとします。
その見込み案件は、今年度の事業予算を達成させるために「絶対受注したい案件」だったとします。
もちろん自分がプレイングマネージャーとしてフロントに立って対応すれば、確実に受注する自信はあるはずです。
しかし、そのようなことを続けていてはチームの底上げに繋がらないので、失注する可能性を含めて、対応を部下に任せなければいけないのです。
もし失注した場合、事業予算が未達になるので、もちろん自分のマイナス評価に繋がっていきます。
このような局面で、全幅の信頼を置いて部下に見込み案件を任せる勇気がある人はどれだけいるのでしょうか?
これはとても勇気のいることだと思いますが、実行するためのポイントは、とにかく見込み案件をたくさん持っておくことです。
つまり、たとえその見込み案件が失注したとしても、後々挽回できるだけの見込客がストックできていれば、そんなに恐怖心はないはずです。
このイメージとしては、全体を俯瞰的に見てコントロールする感じなので、営業部長という立場を実際にこなしながら会得するスキルだと思います。
指導者としての姿を見せつつ、自分は黒子(クロコ)に徹するという態度が営業部長には求められます。
時にはプロジェクト単位で部下に裁量権を渡しておいて、「もし失敗した場合の責任は全て自分が取る」くらいの気概が必要なのです。
このような姿勢を部下はよく見ています。
勇気ある決断ができること
部長職に限らず会社で出世する人というのは、判断力や決断力が優れている傾向にあります。
部長クラスになると、日々の業務を改善することだけでなく、迅速で的確な判断&決断を求められるシーンが増えてきます。
それらの判断や決断が求められるシーンは、会社の業績を大きく左右させる重要な局面だと思います。
この時に最適解を導き出すのですが、このやり方にセオリーはありません。
今まで自分が経験してきたことや、蓄積した知識に基づいて、その状況に対する最適解を都度導き出すのです。
これは決して万人ができるような芸当ではなく、組織を完璧に理解している人にしか出来ない芸当です。
なので、決断を求められた時に迅速な決断を下せない人は、組織が理解できていないということなので、部長職の資質に欠けているのかもしれません。
即断即決できるということは、決断を迫られるシーンまでにある程度の予兆を汲み取って、様々なケースを常に想定しているということです。
それだけコミットメントが強く、覚悟があり、当事者意識も強いということなのです。
営業部長としての心構え
営業部長になることは、出世する上で一つの大きなステップだと思います。
課長クラスまではプレイヤーとして頑張れば誰でもなれると思いますが、部長クラスにはそれ以上のスキルが求められるので、課長止まりの人と部長になれる人では大きな差が出てきます。
そもそも部長になれる確率というのはどれくらいの確率なのでしょうか。
これは会社の規模などによって異なるものの、おおむね10人に1人程度(10%くらい)というイメージがあります。
つまり、部長職までたどり着けない人のほうが圧倒的に多いのです。
したがって、営業部長になれる人というのは、出世レースを勝ち抜いた、それなりに選ばれた存在であると言えるでしょう。
部長職になる人は読書をすべき
部長職になる人は、豊富な知識がなければいけません。
当たり前の話ですが、部下よりも博識でなければ、部下から見た場合、とても頼りなく見えてしまいます。
なので、日頃から読書をする習慣をつけましょう。
「読書は苦手…」という人をたまに見かけますが、部長職の人にとってはそんなこと関係ありません。
読書をすることも仕事の一環だと理解しましょう。
部長職、ひいては経営者として活躍したいのであれば、絶対に読書をすべきです。
ここでは営業部長として活躍する人に読んで欲しい本をご紹介しておきます。






優秀な部下を育成する
色々とお伝えしてきましたが、もしかしたらこの部分が一番重要かもしれません。
部長(リーダー)がやるべき最も重要な仕事とは、優秀な部下を育成することです。
優秀な社員を育成することは、会社の将来にとって大きなプラス要因になりますが、もし部下の育成に成功すれば、自分にとっても大きなメリットがあるのです。
それは多馬力になるということです。
これまでは自分がトップセールスとして会社を支えてきたと思いますが、自分のようなトップセールスが5人、10人いたら売上も5倍、10倍になるはずです。
これが多馬力という考え方です。
これまでは自分一人の「一馬力」で頑張ってきたと思いますが、自分の持っているセールスノウハウを共有して、多馬力にすることで組織は大きく拡大していきます。
つまり、単に指示するだけでなく、チームの関係性を良好にして、自分自身の分身を作ることが、部長になれる人の条件と言えるでしょう。
営業部長がすべきこと
営業部長がすべきこととは一体何なのか?
高い年収を得ている以上、それ相応の役割が求められます。
営業部長がすべきことを端的に言うと「ビジネスの仕組みを構築する」ことです。
前述した通りですが、部長職の人は「リーダーシップ」と「マネジメント」の両軸を回さなければいけません。
このうち、最低限達成しなければいけないミッションは「マネジメント」になります。
つまりこの部分が「ビジネスの仕組みを構築する」ことになるのです。
営業部長になると課長や係長時代のようにプレーイングマネージャーとして活躍していた立場から、マネージャーの立場に意識改革しなければいけません。
いくら優れたトップセールスであっても、セールスマネージャーとして一流とは限りません。
一流のプロ野球選手が、監督としては一流ではないのと一緒です。
しかしマネージャーである以上、「自分が仕事しないでも営業部が回る」くらいの仕組みを作る必要があるのです。
ビジネスの仕組みを構築する
とても優秀な営業パーソンが一人いれば、営業部としての成績は安泰かもしれません。
しかしこのやり方では、そのトップセールスマンがいなくなった途端に、売上が激減するリスクを常に抱えることになります。
そうなってからでは遅いので、営業部長としては個々人のスキルに依存しない、再現性のある仕組みを作る必要があります。
再現性のある仕組みづくりとは、簡単に言ってしまうと「今日入社した新入社員でも売ることができる」ような仕組みを言います。
このような仕組みづくりを行うことがマネジメントなのです。
これは感覚的に「事業を創る」ことなので、決して簡単ではありません。
セールスだけでなく、マーケティングもセットになってくるので、かなり幅広い分野の知識が求められます。
壁は高いですが、もしこれを乗り越えることができれば、独立起業も視野に入ってくるはずです。
営業部長に求められていることは、組織全体をトータルマネジメントをすることなので、そのような心構えで仕事をするようにしましょう。