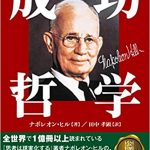世の中や生活が複雑になってくる。
余暇が増えれば、価値観が多様化する。
それに伴い、人々は自分自身の時間を大切にし、充実させようとするから、逆に言えば、労働時間の多少にかかわらず、時間が無くなってくるんです。
これは昭和59年(1984年)に藤田田が語った名言ですが、まさに現代社会そのものだと思います。
人々の時間がなくなることを予想し、ファーストフードの成長性を予見していたのです。
女を狙って商売すれば必ず成功する。
反対に男からカネを巻き上げるのは女の10倍難しい。
男はカネを消費する権限を持たないのである。
また、口に入ったものは必ず消費され、排出される。
確実にカネが入ってくる。
こんな商品は他にはない。
マクドナルドは女性とファミリー層をターゲットにしました。
確かに食の流行は、女性を起点にしているケースが多い気がします。
そして家庭の財布を握っているのも女性(母親)ですよね。
藤田田が唱える商売の基本は「女」「口」「時間の節約&短縮」「簡便化」の4つに集約されるのです。
世界には安くて良質な製品と、それを生み出す開発力、技術力が埋もれている。
このビジネスチャンスを発掘すれば、日本ではまだまだ商売になる。
日本という狭いステージで考えるのではなく、世界規模でビジネスは考えるべきだと藤田田は語っています。
必要なのは、絶対100%成功するという思い込みではなく、絶対成功する、させてみせると自分で信じることである。
この言葉はつまり「思考は現実化する」という意味の名言です。
ナポレオン・ヒルが残した同名の名著がありますよね。
これは成功哲学をまとめた世界的な名著なので、ビジネスパーソンは絶対に読むべきだと思います。

ナポレオン・ヒルの名言集が知りたい人は下の記事をご覧ください。
経営は日本人、アメリカは技術情報を出すとはっきり分けないとダメ。
日本は教育レベルが違うし、独自の文化を持つ。
それに疎いアメリカ人が来て命令しても人は動かない。
これが日米合弁の失敗の理由だ。
昭和44年、日本国内における外国資本によるレストラン事業が完全自由化されました。
このタイミングで様々な外資レストランが日本に参入しましたが、結果的にはことごとく失敗に終わります。
その中で、圧倒的な成功を見せた日本マクドナルドについて語った名言です。
実は藤田田以外にも、大手総合商社、スーパーチェーン、大手食品メーカーなどが、マクドナルド本社へ次々とオファーを出したそうです。
しかし米マクドナルドの社長であるレイ・クロックは、ほぼ無名だった藤田田と契約する事を選びました。
しかもその内容は30年間の長期契約で、契約更新の権利は藤田田が持ち、ロイヤリティは売上高のたった1%という破格の待遇だったのです。
資本比率は50%づつでしたが、経営権は全て藤田に委ねられました。
つまり「アメリカマクドナルド本社からアドバイス(助言)は受けるが、オーダー(命令)は受けない」という契約を交わしたのです。
全てにおいて非常識な契約でしたが、レイ・クロックは藤田田という人間は信頼できると判断したのです。
レイ・クロックはアメリカマクドナルドの創業者ですが、自伝があるので興味がある人は読んでみてください。

契約というのは結婚と同じなのだから、離婚の用意をしてから交わさないとね。
この言葉はアメリカ式の契約を賞賛した名言です。
マクドナルドと交わした契約書の中には「Death Of DEN FUJITA(藤田田の死)」という文言があったそうです。
つまり藤田田が死んだ場合には契約を解消するという内容です。
このような内容を「失礼だから…」という理由で日本人は契約書に入れ込まないですが、契約を重視するアメリカでは記載してしまうのです。
このような点がアメリカのいいところだと、藤田田は語っています。
サービスで一番難しいのは、サービスというものは在庫ができないということです。
マクドナルドはフランチャイズシステムなので、たくさんのマニュアルが存在しています。
- バンズの厚さは上部が22~28mm、下部は16mm
- パティは45gにする
- パティは32mmの厚さの鉄板で焼く
- パティを焼く鉄板の表面温度を華氏370度に保つ
- 注文を受けてから32秒以内に、摂氏62度で顧客に出す
このようなマニュアルがあればその通りにするのですが、サービスはマニュアル化するのが難しいと藤田田は語っています。
東京から導入していくことによって、それまでの常識を逸脱したものでも全国が注目するんですよ。
日本マクドナルドの第1号店は、昭和46年7月20日にオープンしました。
場所は東京のど真ん中、銀座三越です。
マクドナルドのアメリカ本社は銀座三越への出店に難色を示したそうですが、藤田田はそれを強行したそうです。
藤田田は「坂道の上から石を転がせば、石は自然と勢いを増して転げ落ちていく」と考えていたのです。
結果的に、この戦略は大成功を収めます。
銀座の街中を若い人がハンバーガー片手に食べ歩くのを見て、「日本の食文化は絶対に変わる!」と確信した、もう一人の人物がいました。
それが日清食品創業者の安藤百福です。
安藤百福は日本マクドナルドの成功を見て、カップヌードルを若者が銀座で食べ歩く姿を想像したそうです。
実際に1年後、安藤百福もカップヌードルの試食販売(デモンストレーション)を銀座で始めて、藤田田と同じく大成功を収めます。
安藤百福の名言集は下の記事をご覧ください。
ハンバーガーのようなビジネスは、一個一個売っていくんですから、満塁ホームランはない。
小売業には逆転満塁ホームランのような起爆剤がないので、一個一個地道に売っていくしかありません。
これは藤田田が掲げる商売の信念であり、マクドナルド商法の基本となっています。
日本人はフランスに対しては憧れみたいなものがあるんですが、当時はアメリカに対して複雑な感情を持っていました。
そこでアメリカってことがわからないようにして始めたんです。
藤田田は、店名を「マクドナルド」にしたことが、日本で成功できた理由の一つだと語っています。
実は、本場アメリカでのマクドナルドの発音は「マクダーナルズ」なのです。
これだと語呂が悪いということで、3音ずつ切れる「マクド・ナルド」にカタカナ表記を変更したのです。
さらにマクドナルドの店内には、アメリカの国旗や地図を出すことを禁止して、アメリカ色を全て取り去ったのです。
このような工夫がハンバーガーというアメリカ文化を、アメリカ製でも日本製でもない、いわゆる国籍不明の外来品というオブラートに包ませたのです。